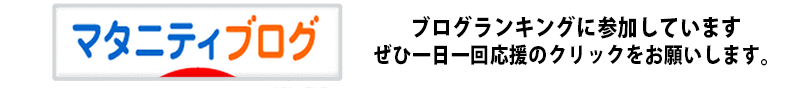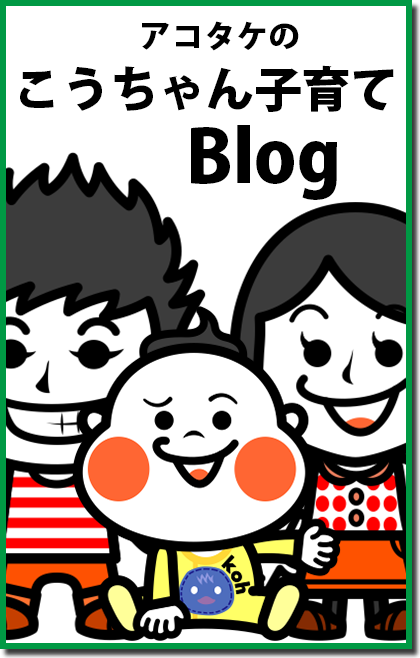はじめてのチュー

昭和四十六年の十二月末まで、小川ビルで四人の共同生活は続いたのだが、岡村さんと平林さんが結婚することになり、共同生活を解消することにした。
四十六年の二月より佐藤憲行さんが会の職員に加わったこともあって、思いきって、独自の本部を借りることにした。
五反田駅に近い、マンション型の貸ビルで六畳と台所キッチン付きで月三万円の家賃だった。
ダイニングキッチンにグリーンのカーペットを敷き事務所にしていた。
その日も母ちゃんは一人で事務所にやって来た。
父さんもたまたま一人で、会計の整理をしたり、原稿を書いたりしていた。
母ちゃんはまた話しはじめた。
「会長さん証券会社に勤めていたんでしょう?証券会社の男の人真面目な人ですか……?」
「証券会社の人がどうかしたの?」
「アノネ、私、山一証券に勤めている人とお見合いをしたの」
「品田さんまだ二十歳になったばかりだろう」
「そうなんですけど、お母さんが無理矢理にしなさいというので……」
「それで養子になってくれるの」
「そうなんです。養子になってもいいんですって」
「品田さん自身は、その人とあってみてどう思ったの」
「お見合いをしたあとで、二度ほどデイトをしたんです。でも、どうしても好きになれないんです。約束の時間をキチンと守らなかったり、外交的で口が上手すぎるのもイヤなんです」
「イイ男だったかい」
「それがね、背が低くて、私より十センチぐらい低いんですよ、それで円い顔をしていてね、エビス大黒さんみたいに耳が大きくてね」
その話をききながら父さんは、
“オレの気持をたしかめようと思ってお見合いをしたと言っているのだろうか、それともただなんとなく、話をしたいという気持で話しているのだろうか”と考えてみた。
そんな話をしばらく続けたあと、
「品田さんキッスしたことあるかい」
父さんはききながら母さんの顔を見た。
母ちゃんは一寸答えにつまって、
「エエ、まあ、アリマセンワ」
「いや、その答えかたでは、あるな」
「まあ、イヤーネ」
「あるな、きっと」
父さんはわざとつぶやくように言った。
「…………」
「………」
父さんは、ベンを走らせながら、
「品田美津子さんとキッスをしたくなったな」
といった。
「まあ、コワイワ」と母ちゃんは、何だか、うれしそうな.同時にはずかしそうな、奇妙な顔をした。
「いいだろう、キッスは楽しいもんだよ」
「まあ、知りませんわ」
「…………」
「…………」
「本当にしたくなった」そう言って、父さんはそれまで走らせていたベンを置き、腰を浮かした。
テーブルの反対に座っていた母ちゃんは、反射的に逃げるような仕ぐさをしたが、逃げはしなかった。父さんは、笑いながら、
「キッスは楽しいもんだよ、もし知らないのならおしえてあげる」と言いながらテーブルの回りを廻って母ちゃんに近づくと、母ちゃんは、
「はずかしいわ、コワイワ」と言いながら、反対の方に身体をよけてテーブルを一回転した。
しかし、それ以上に、逃げるということもしなかった。
みんなの会の事務所は、いつ誰が来ても、自由に出入りできるように、という考えから鍵はかけていないことが多かった。母ちゃんが来ていた時も、もちろん鍵はかかっていないのだから、本当に逃げようと思えばわけなく逃げることはできたのだ。結局小さなテーブルを囲んで鬼ゴッコのようなことをした。だから父さんはキッスをしてもいいんだなと思って、母ちゃんの手をにぎり、母ちゃんとはじめてのキッスをしたのだ。
最初、手で口元をおおっていたが、それは女性としてのエチケット程度のもので、あとはずなおに父さんのキッスを受け入れていた。
その時、一寸したハグニングがあったんだ。というのはキッスをしている時、来客がいきなりとびらを開けると困るからと思って、父さんが鍵をかけたんだ、そしておもむろに落ちついてキッスをしていたんだ。そしたらしばらくして、ドンドンとドアをたたくんだ。
しばらくたてばあきらめて帰るだろうと思って、あわててキッスをするのをやめて、息をひそめていたんだ。
しかし、外の人はいっこうに帰ろうとしない、そればかりか、鍵のかかっているにもかかわらず取手をガチャガチャまわして、いまにもこわさんばかりのいきおいなのである。
「おかしいな、ここはいつも鍵はかけていないのにな」と話している声もきこえる。
中にいる父さんと母ちゃんはヒヤヒヤだ。キッスしていたのがバレては困ると、それでも息をこらして黙っていたが前よりいっそうはげしくドンドンガチャガチャ、とても帰りそうもない。
父さんはたまりかねて別に用もないのにトイレに入った。そして口をぬぐっていると母ちゃんが、「玄関、開けましょうか」といって、結局母ちゃんが、鍵を開けた。
外に立っていたのは、泉岡武志おじさんとおじさんが一緒に仕事をしているという、父さんの知らない中年の男の人二人だった。
父さんはテレ臭さをグーットおさえて平然とした態度をよそおいながら、二人にコーヒーを出した。
“口の回りに口紅がついていなければいいけどなー”とドキドキしながら、
「いや、品田さんが頭がいたいといっていたので、静かにしてあげたいと思ってね」
となんともトンチンカンな弁解めいたことを口にした。
武志おじさんと中年の男の人は、そのことには何もふれられず、景気の話や、仕事の話などをしていた。しかしふれられなければ、ふれられないで、“中で二人が何をしたのはバレたかな”と妙な不安にかられた。そのとき母ちゃんは割りと平気な顔をしていた。
そのことは、ズーット二人だけの秘密になっており、おしゃべり好きの母ちゃんも誰にも内証だったらしい。そして父さんは母ちゃんとはっきり結婚することになった頃、坂元和夫さんに打ち明け話にしただけだった。
母ちゃんと父さんがはじめてキッスをしたのは、四十七年三月、母ちゃん二十歳。父さん三十歳の時だ。
お互いに愛を確かめあって、というよりは、若い女性と、若い男性とがなんとなく気軽な気持で、ということであったと思う。
だから、それから後、二人の仲が急に進展したということもない。
強いて言えば、それから一週間程して、また母ちゃんが一人でやって来て、
「今新潟から帰って来たのです。これおみやげです。お父さんが駅で待ってまずから」
と塩からのちいさなビンずめ一個を玄関で渡して、そそくさと、はずかしそうに帰って行ったことがある。その時、父さんは、
“彼女はボクに好意を持っているのかな”と思ったぐらいのものである。
しかし、その後も母ちゃんが特別何かをしてくれるということもなく、父さんも別にどうということもなく、普通の会員として積極的に参加する一人の女子会員でしかなかった。
結婚をする一寸前「生まれて一番最初にキッスをしたのはいつ」ときいたら「高校生のとき」と母ちゃんは答えた。
母ちゃんはすすんでるという感じだ。

こわいわ!!
丁度その頃、そう二十歳の時、両おばあちゃんの強い勧めで、山一証券に勤務している人とお見合いをしたの。
仲人さんからは返事の催促。
両おばあちゃんは、その男性が“養子になってもよい”というので大乗り気。
母ちゃんは気がすすまないのに、話を勧めようとしていたの。
母ちゃんは、とても悩んだの。父さんも、みんなの会を創る前に、証券会社に勤めていたということを知っていたので、いろいろ聞いてみようかな、と思って、会の本部に行ったとき、その話をしたの。
父さんは、自分の都合のいい方にいい方に勝手に解釈しているようだけど、父さんの気持を確かめてみようと思ってお見合いの話をしたのではないのよ。
そお、その時、父さんがそばに寄ってこようとするのでテーブルの回りを、一回位ぐるぐる回り、怖い怖いという印象が残っているだけ。
父さんが言うように、本当に嫌いだったらドアーを開けて逃げていたかもしれないわね。
泉岡のおじさんがドアーを開けようとガチャガチャ音をたてているので、会ってどんな顔をしようか、話をどうしたらよいのか、スリル満点ドキドキ。
父さんが、
「君は具合が悪いから休んでいたことにしよう」と言ったので「ウン」とうなずき、
父さんがドアを開け、母ちゃんは、おじさんたちが入って来てからもしばらくマットレスの上に横になり、病人の真似をしていたの。
健康だけがとりえの母ちゃんを知っている泉岡おじさんは、きっとおかしいな、と思ったに違いないわね。
↑上に戻る